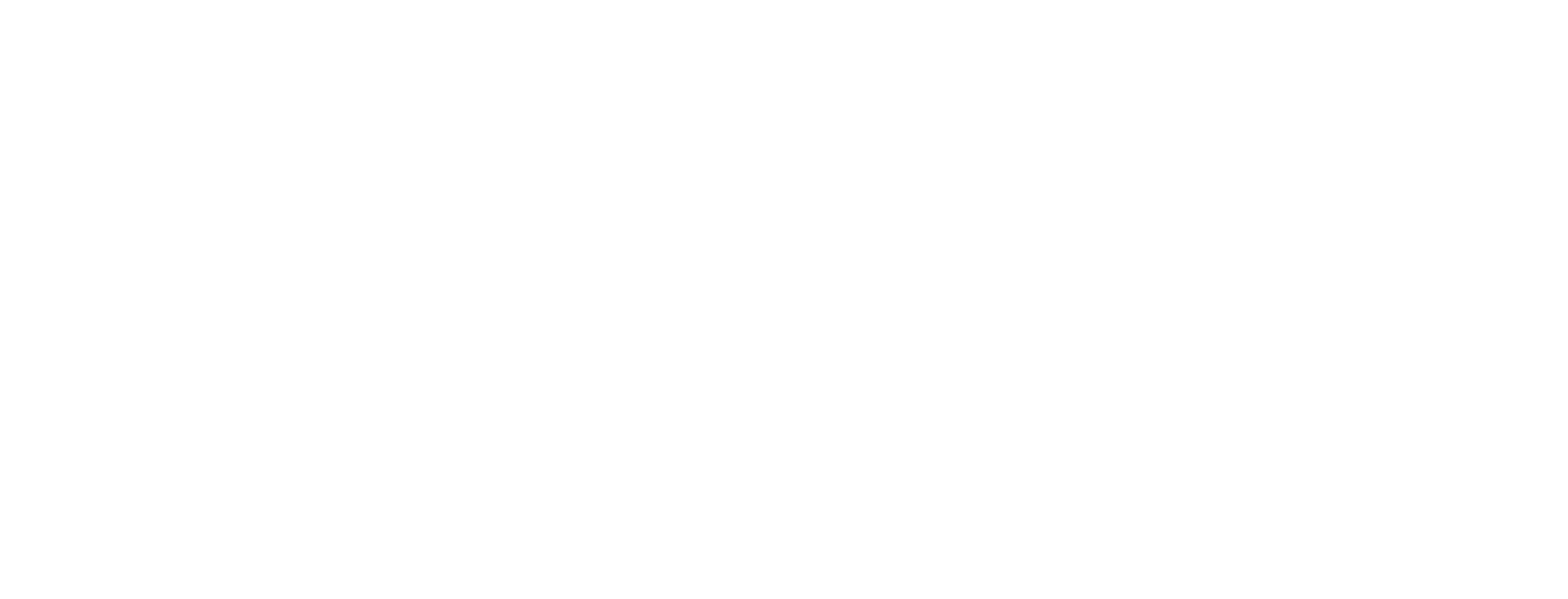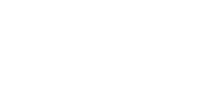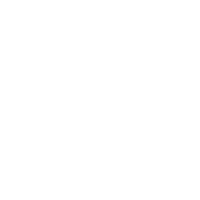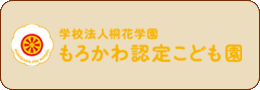- HOME
- 寺院紹介
寺院紹介
副住職のご挨拶
檀信徒関係者各位みなさま、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
常にみなさまのご先祖様の回向、そしてご多幸を本尊様ご宝前にて読経祈念する様心掛けております。日頃住職とともに、本堂・薬師堂での読経、葬儀、ご法事、ご祈願、お塔婆・お位牌・御朱印の浄写等檀務に精励させていただいております。
宝蔵寺を継承し、43代住職に就任できる様、精進努力をしてまいります。何卒よろしくお願いいたします。

宝蔵寺の歴史
古河市諸川に所在する宝蔵寺は、慈光山大善院と号する新義真言宗豊山派の寺院で、ご本尊は不動明王です。
寺伝によれば、宝蔵寺はその創建を室町時代とし、文明年間(1469〜87年)に住持の性宥によって中興されたと伝えられ、創建は文明年間以前の室町時代と言われています。宝蔵寺には、鎌倉時代前半の制作になる木造薬師如来立像一躯と木造大日如来坐像一駆が伝存する。このうち薬師如来は宝蔵寺境内にある薬師堂のご本尊で、その堂宇は前記の山川景貞の寄進という寺伝を持つ(現在の堂宇は江戸時代以降の建物)ことから、どこか他所からの流入品などではなくもともと現在地に所在していた可能性が高いと言われています。
寺伝によれば、宝蔵寺はその創建を室町時代とし、文明年間(1469〜87年)に住持の性宥によって中興されたと伝えられ、創建は文明年間以前の室町時代と言われています。宝蔵寺には、鎌倉時代前半の制作になる木造薬師如来立像一躯と木造大日如来坐像一駆が伝存する。このうち薬師如来は宝蔵寺境内にある薬師堂のご本尊で、その堂宇は前記の山川景貞の寄進という寺伝を持つ(現在の堂宇は江戸時代以降の建物)ことから、どこか他所からの流入品などではなくもともと現在地に所在していた可能性が高いと言われています。

したがって前述の創建年次からすれば、宝蔵寺成立以前に当薬師如来を祀る小堂があったことになります。または創建年次を鎌倉時代にまで遡ることができるのかもしれません。いずれにしても、宝蔵寺には室町時代前半の両界曼茶羅が現存するから、寺伝同様少なくとも室町時代前半には同寺は創建されていたものと考えられ、その地は仏教に有縁の地でした。江戸時代になると、宝蔵寺は本山を高野山金剛三昧院とし、四ヵ寺の末寺と七カ寺の門徒を有する、いわゆる田舎本寺などと呼ばれる寺院でした。また、三代家光の時(慶安元年・1648年)以来、諸川村内に八石の朱印地(免税地)を有していました。
境内は「御朱印」となっていて、朱印地であった。その境内には客殿・庫裏・寝所の居住空間があり、薬師堂と香取宮を始めとする神社が五社、そのほか楼門・長屋門がありました。また、境外(諸川村内)には同寺が管理する(別当)神社が14社ありました。このように、少なくとも室町時代前半まで遡ることができる宝蔵寺は、中興以来連綿として受け継がれ、田舎本寺として地域に受容された江戸時代を経て、今日もなお諸川の、あるいは三和地区の由緒あるお寺として法灯を守り続けています。その結果として、仏像など仏教工芸品や多くの古文書などが現在まで遺存している。この貴重な地域の文化財を後世まで保存していくことがわたしたちに与えられた責務です。
寺院概要
| 社名 | 真言宗豊山派 慈光山大善院 宝蔵寺 |
|---|---|
| 所在地 | 〒306-0126 茨城県古河市諸川342-1 |
| TEL | 0280-76-1143 |
| 受付時間 | 9時から16時 |